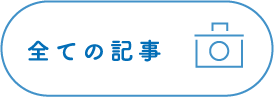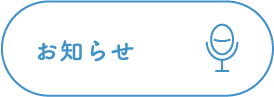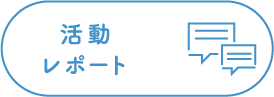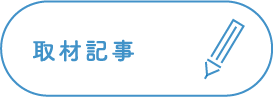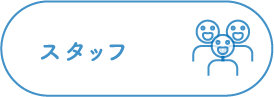【fukaレポ】取材ワークショップ
こども編集部の核となる、取材の記録です。
6月1日、橋の科学館で取材のワークショップがありました。
今回も、「こども編集部のこどもとおとなの間」を自称する、ふうかが書いています。

最初は、どんなことに気をつけて、どんなところに注目して、どんなイメージで、取材や編集をするのかを聞きました。
こどもたちの周りには、とてもたくさんの種類のメディアがありますが、今回は雑誌のイメージで、こどもからの目線を素直に書くことを意識します。
難しかったところがあれば、それも素直に表現しよう、という、大人からの理想もありながら、こどもたちは展示室に向かいました。

副館長さんから説明をしていただきました。やはり、明石海峡大橋の建設に関する専門的な展示なので、入ってすぐは、こどもたちの反応からも、わかりにくそうかなと思っていました。
でも、進むにつれて、こどもたちが注意深く聞いているように見えてきました。印象に残った言葉はメモをして、副館長さんの方を見ながら真剣に聞いていました。その真剣な目は、本当の記者と同じだと思います。
自分のセンサーに引っかかるところを探すように、小さい情報も逃さないように、聞いたことを書く姿は、肉食動物が獲物を探すシーンと似た迫力がありました。
その一方で、後ろの方にいる中学生は、取材に慣れている空気をまとっていて、余裕の表情でした。

一通り説明してもらって、質問の時間になると、堰を切ったように質問が出てきました。
「明石海峡大橋に、人は何人乗れますか?」「明石海峡って、どこからどこまでですか?」と、自分が聞きたいことは前のめりで質問していました。
副館長さんもその勢いに乗って、いろんな話を喜んでしてくださいました。
「聞きたい」という意欲が、こども編集部の流れを作っているんだな、と実感した時間でした。
聞きたいと思って来る子がほとんどなので、学校とは違って、周りの子に刺激を受けながら、お互いに積極性が高まっていくのかなと思います。これで思い出したのが、中学生のときにした理科の実験です。
試験管に硫黄の粉末とスチールウールを入れて、ガスバーナーで加熱すると、火から離しても、しばらく反応が続きます。
これは、硫化鉄ができる熱が、近くの硫黄と鉄をまた反応させるからです。


新聞を書く時間になっても、質問が終わらなかったので、新聞は各自の宿題になりました。
家で仕上げるために、気になったことは全て聞いて帰ろうと、最後までじっくり質問している子も、方向が定まってほとんど書けた子も、それぞれ自分が納得することを進められるのが、こども編集部のいいところだなと思います。
私は、美術の授業で「もっと時間があれば、もっと丁寧に、納得するまできれいに塗れたのに」と思うのが嫌いでした。
絵を描くことや、工作することはとても好きだったはずなのに、美術の時間は苦手でした。急かされて、何回も妥協して、簡易的な完成品を提出しないといけないのが、苦痛でした。
「1年で油絵1枚を完成させる、とかでいいのに」と思っていました。
なので、自分が「これがいい!」と思えるまでじっくり取り組める場所があるこどもたちが、羨ましいです。
こどもたちの、「意欲の”あかし”」を感じた、橋の科学館での時間でした。
レポ*サポーターfuka